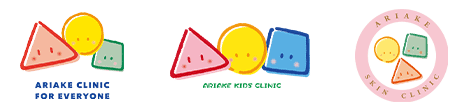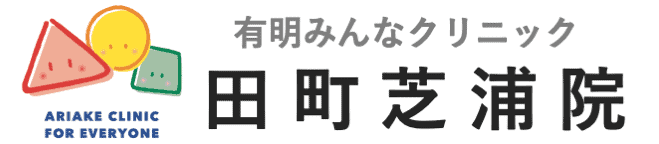2025.03.06 「共感による傾聴の大切さ」
クリニックでは毎日多くの患者様が来院され、忙しい日々が続いています。そんな中で、「まず理解に徹し、そして理解される」という第5の習慣の大切さを改めて感じる出来事がありました。
先日、自費診療の診察が朝から大きく遅れてしまい、予約時間を過ぎても呼ばれない患者様がいらっしゃいました。受付としては、2診に回せる方はご案内し、調整できる限りの対応をしました。しかし、予約時間を過ぎても診察が進まなかったことで、患者様からお叱りのお言葉をいただきました。

一見、対応としてはできる限りのことをしたと思っていましたが、振り返ると、患者様の立場になって考えきれていなかったことに気づきました。
以前の来院時も予約時間通りに診察が進まなかったこと
その方には次の予定があり、遅れることが大きな負担になっていたこと
診察の遅れを早めに伝えず、患者様の焦りや不安を増してしまったこと
これらが積み重なり、「大切に扱われていない」と感じさせてしまったのではないかと思います。
共感による傾聴の大切さ
7つの習慣では、最も高度な聞き方のスキルとして「共感による傾聴」が挙げられています。
ただ話を聞くだけでなく、「相手の身になって聞く」ことが重要です。
今回の出来事を振り返ると、私たちは「自分たちの事情」を優先しすぎていたかもしれません。診察の遅れを伝える際も、患者様がどんな気持ちで待っているのかを想像し、「ご不便をおかけして申し訳ありません」と伝えるだけでなく、「お時間が気になりますよね」「次のご予定に影響がないでしょうか」と、患者様の気持ちに寄り添う言葉をかけられたのではないかと思います。
今後に向けて
クリニックの業務は忙しく、すべての状況を完璧にコントロールすることは難しいですが、「患者様がどういう状況にいるのかを考え、一人ひとりと向き合うこと」は常に意識していきたいと思います。
診察が遅れそうな場合は、早めにお声かけする
ただ遅れを伝えるのではなく、患者様の不安に寄り添う言葉をかける
自分たちの事情だけでなく、相手の気持ちを言葉にして伝える
これからも、患者様にとって安心できるクリニックであるために、コミュニケーションの質を高めていきたいと思います。